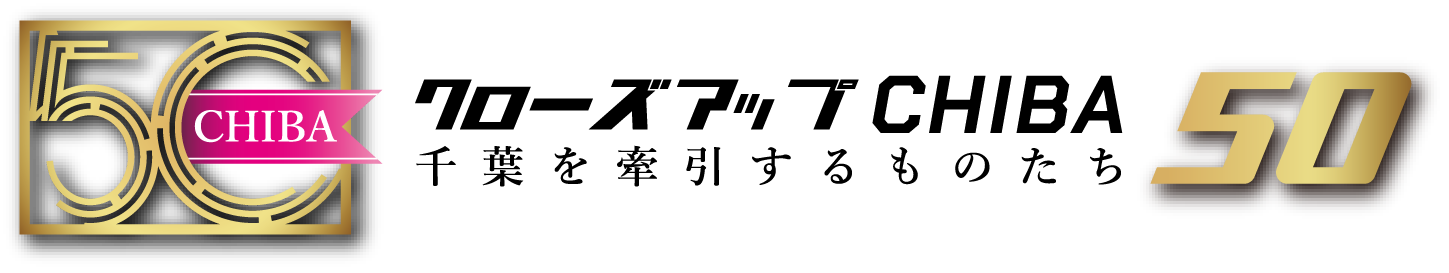1980年、東京都出身。高校中退後、製造・溶接業の現場で経験を積みつつ、自らの興味でCAD/CAMや工作機械の技術を習得。20代半ばより車・バイク部品の製造を手がけ、20年以上にわたり、設計から製作まで一貫対応するエンジニアとして活躍している。
https://technical-works.jp/四街道市のカスタムパーツ専門メーカー
千葉県北西部の住宅街を抜けると、鉄と油の匂いがわずかに漂う小さな工場に行き当たる。看板には「Technical Works」の文字。オートバイや四輪の金属部品を一気通貫で設計・製造している会社である。他社に真似できない高い技術と豊富な経験を基に、基本整備、修理から高度なチューニングまで対応が可能だ。
テクニカルワークス代表の杉田大(すぎたまさる)が工作機械の切削音を背に「やっぱインチキははしたくないし、ハッタリや嘘もつかないように心がけています」と言い切る様子は、職人というより修行僧の風格すら漂う。

独学で積み重ねてきた技術と誇り
創業は2004年、と登記の上ではそう記されるが、実の年月はもっと深い。杉田は1980年生まれ。高校を約2週間で辞め、工場で働きながら溶接と切削を覚えた。20代半ばで旋盤を買い、30代でNC旋盤とマシニングセンターを導入。CADやCAMも独学で身につけ、気づけば二十余年、金属と向き合い続けてきた。「好きなバイクでサーキットを走っているうちに、手に入らないパーツは自分で作ればいいや、と思って始めたのがきっかけでしたね」
コツコツ積み重ねた研鑽は、いつしか誰にも真似できない類まれなる技術となって、削り出した部品や溶接などに伝わって成果として現れる。あなたのパーツを積んだマシンが各ショーで優勝した、対応していただいたおかげでタイムが良くなった…表彰台で輝くマシンを遠巻きに眺めながら、杉田さんはこぶしを握りしめる。OEM供給だから社名はほぼ出ない。それでも、自分が削り出したりした部品やバイクが風を切り、タイムを縮めたり、楽しんでもらえたら。そう思うだけで胸が熱くなる。以来、“表には出ない誇り”こそ会社の礎となった。

「他社でできないモノこそ」
旋盤2台、フライス盤3台、マシニング2台、溶接機、治工具など。工房にはプロトタイプ開発を一人で完結できる機械が並ぶ。要望があればミルシートなどを付けたり、材料や処理、加工工程など聞かれれば丁寧に答えるようにしているという。「正直者がバカを見ない」ためだと杉田は語る。
「他社で出来ないと断られたんです、何とかなりませんか?という依頼が来ることがよくありますが、そういうときは特にやる気になりますね」と言うその言葉どおり、依頼主が北海道でも沖縄でも、部品が届けば即座に杉田は加工プランを提案して対応する。リピーター率が高いのは、そんな負けず嫌いの気質ゆえかもしれない。
もちろん、順風満帆とはいかないこともある。機械が壊れれば修理費は数十万はくだらない。狭いながらも何台もの機械があり、維持するだけでもかなりのランニングコストがかかる。落胆もつかの間、翌朝には復旧プランを練り、さらに高精度の治具を考えている自分に気づく。失敗しても「次はどう挽回するか」という材料になり、寸暇を惜しんで工具を研ぐ日々が続く。
そしてまた、品質保証の最初の一歩は、作り手自身が健康でいることだという。「ケガや病気で納期を飛ばせば更に迷惑をかける。最近は特に体調管理も仕事のうちと考えています」

やってみなきゃ始まらない
これからの目標は、さらなる品質向上とブランド力の確立だと杉田は語る。「お客様が“これ、テクニカルワークス製だぜ”、と誇ってもらえるような部品を更に増やしたいですね」
最後に、これから飛び込んでくる世代をどう見ているか尋ねた。「たとえ失敗しても、損しても、やはり自分でやってみなきゃ始まらない。今日がマイナスでもプラスにしてやるぜ!みたいな覚悟があれば、道は開けると思います」
静かな工房で今日も切削音や溶接音がリズムを刻む。言葉は朴訥でも、出来上がったパーツの輝きや装着されたバイクの佇まいがその真意を雄弁に物語っていた。