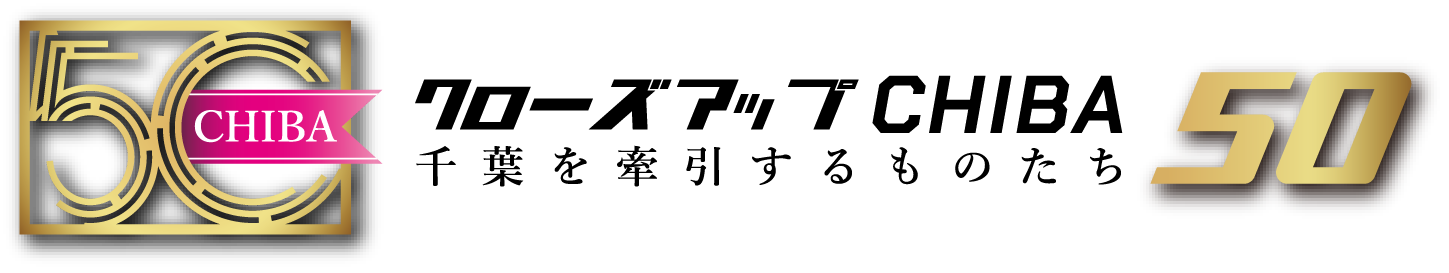1971年兵庫県西宮市生まれ。市川工業高校卒業後、1995年に稲村工業へ入社。現場監督として施工管理に従事し、2012年取締役就任。福利厚生改革など組織改善を進め、2024年に創業社長の後を受け代表取締役に就任。水道本管更新工事を中心に30年の実績を積み、社員と家族の満足度向上を経営方針に掲げる。現在も現場に立つ。
https://inamura-k.co.jp/千葉県民の暮らしの根底を創る会社
約10,000キロメートル。これは、千葉県内の地下に埋まっている水道管の総延長だ。アスファルトの下を、水道管が静かに軋みながら、今もなお横たわっている。東京の日本橋から市川市、船橋市を抜け、千葉県千葉市中央区まで至る、国道14号線。ヘッドライトがまだまばらな闇の中で、速水雅之は路面に立ち、耳を澄ませる。
速水率いる稲村工業株式会社は、行政と二人三脚でこの見えない血管を更新し、街の新陳代謝を支える、まさに小さな臓器だ。従業員はわずか12名。だが、この12の鼓動が止まれば、千葉県民の暮らしのリズムもたちまち狂ってしまう。

福利厚生の真の目的
稲村工業は昭和51年の創業以来、千葉の地下で水が流れる道をつくり続けてきた。水道管の耐震化、水道本管の更新、下水道の改修…いずれも派手な看板を掲げる仕事ではない。しかし、たとえば震災で水が止まったとき、人々は初めてその名を探す。ライフラインとは文字どおり、人の生をつなぐ線であり、その継ぎ目を縫う手は、工場の旋盤よりも繊細で確かな感覚を要する。
兵庫県西宮で生まれ育った速水は、24歳で会社に入った。入社理由は、たまたまだという。結婚を機に「ちゃんと稼げる仕事」を探し、掴んだ縁。上司にも恵まれ30年以上、彼は現場に身を投じ続けた。
東日本大震災、液状化した浦安の街で、泥に膝まで埋まりながら、復旧工事に明け暮れた1ヶ月があった。バックホウの油の匂いとガス灯の明滅の中で、彼は「誰かに水を届けるために、自分は生きている」ことを骨に刻みつけた。
そして2024年春、代表取締役へ就任した。「働き方改革」も始まっていない平成の時代を知る男は、まず「社員を大事にする」ことに舵を切る。企業年金の導入、空気清浄機の設置、制服の刷新。細部は小さくても、そこに込める意図は大きい。「これらは、本人のためだけじゃないんです。彼らには、帰宅すると待っている家族がいます。家族の方にも、稲村工業と付き合って良かったと、心から思われたいので」

稲村工業式組織論
稲村工業の強みはシンプル。千葉県企業局発注の水道本管工事で30年の実績を積み、高いリピート率を誇る、安定受注。その実績を可能にしているのは、約10名というミニマム編成に秘めた柔軟性だ。
速水は「完璧な監督」を求めない。2名、3名で現場を張り、それぞれの得意分野を細分化するのである。住民対応が巧みな者、どんな現場でも測量を任せられる者、PCで図面を操る者…それぞれの個性をパズルのように組み合わせ、プロジェクトを駆動させるのだ。
ICTも導入した。クラウド図面共有と遠隔カメラで、深夜の現場でもデータはリアルタイムに本社へ届く。だが最新機器より重要なのは、路面を叩くドリルのリズムを耳で覚えた職人の勘だ、と彼は笑う。技術と感覚…硬質な鋼管と、水面のさざ波のようなチームワーク。その対比こそ、この会社の詩学であり、そして積み上げてきた速水の仕事観でもある。
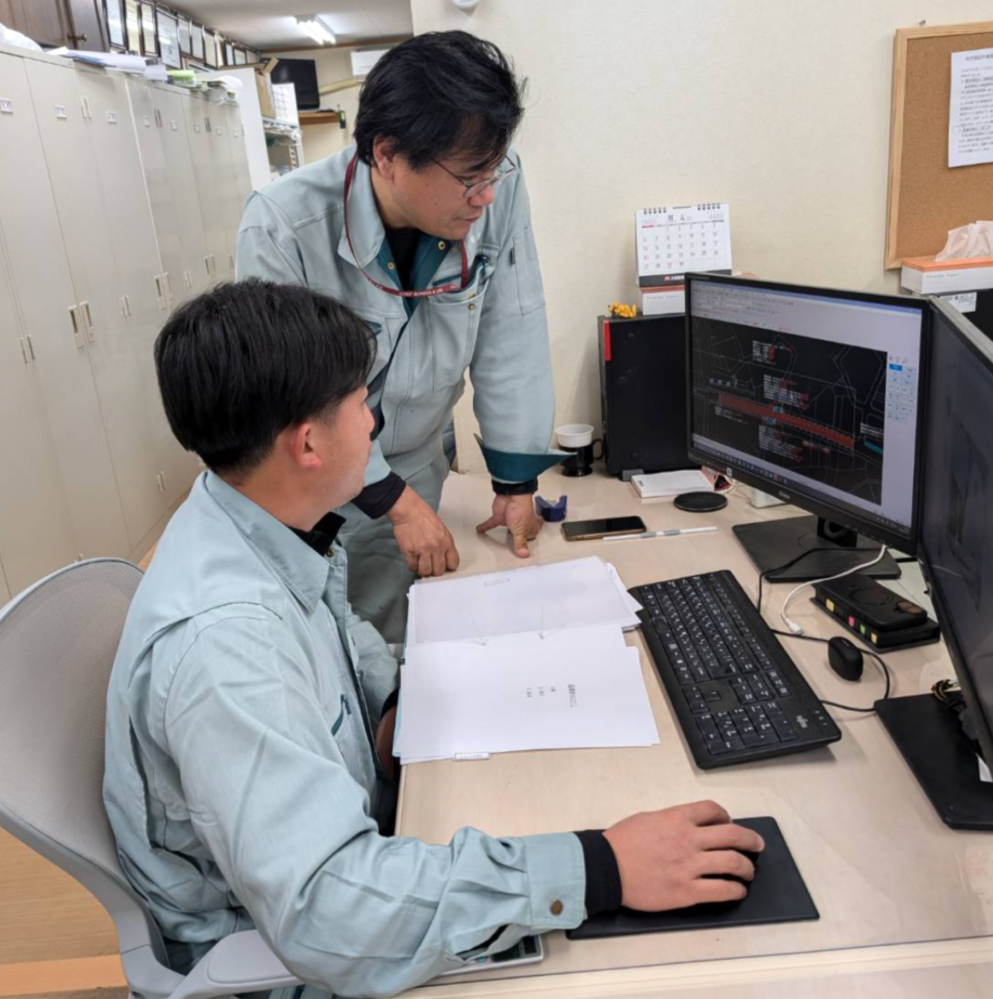
自分らしく
目標を問われると、速水は少しの沈黙の後「まだ模索中です」と言った。けれど、その沈黙は逃避ではなく、真摯な空白に他ならない。安定した受注の上にあぐらをかくのではなく、社員一人ひとりの「自分らしく」を丹念にすくい上げ、会社という器の形をゆっくりと、しかし強固な意志を持って確実に変えていく。その、芯の太さが垣間見える。
若者へのメッセージを、と求めると、彼は照れくさそうに笑ってこう結んだ。「自分らしく、そして何事にも前向きに歩いてみるのが大事だと思います。単に頑張ること自体はできますけど、それだと次第に疲れてきますから。私も、若い社員でもなるべく自分らしさを出せるような環境をつくるようにしています。自分らしさを出すことで積み上げた成果には、ひときわ光るものがありますね」
都市の灯が落ち、夜が深くなるほど、地下を走る水音は澄む。稲村工業は、その透明な響きを聞き分ける耳を持っている。12人の小さな鼓動は、今日も千葉の地層をその手で震わせ、見えない未来へと脈打ち続ける。